僕はこれまで3社のスタートアップ案件に参画しました。
「スタートアップって気になるけど、実際どうなの?」
と思っている人もいるのではと思います。
そこで、3社のスタートアップで仕事をした経験がある僕が、その特徴や思ったこと、向いている人、向いていない人をお伝えしようと思います。
スタートアップ案件に興味がある、スタートアップへの転職を検討しているなど、スタートアップについてリアルな情報を知りたい人のお役に立てれば幸いです。
僕が参画した3社のスタートアップ
僕がこれまで参画した3社のスタートアップは以下のような会社でした。尚、全て社員としてではなく、業務委託としての参画です。
①スタートアップA
創業から参画。創業者は元エンジニア。
人間関係に恵まれ、僕にとってはとても働きやすい会社でした。最大10名ほどのメンバーがいました。僕は週1のみ稼働。
サービスを3つ作りましたが、1つはニーズがないと判断しローンチを断念。残り2つはローンチしたもののユーザーのニーズに合わずほとんど使用されなかった。よって売上の見込みが立たない状況に。途中、エンジニアの大量離脱もあった。
結局、売上の見込みが立たず、資金枯渇の恐れが出てきたため開発チーム全員が離任。
②スタートアップB
既にサービスはローンチされており、サービスの月の売上が安定して1億を超えていた。「成功しているスタートアップ」と言って良い会社。
僕が参画した時点で創業7年経っており、社員も60名を超えていた。
開発チームもフロントとバックエンドでチームが構成されており、僕はバックエンドチームに所属。7名ほどのチームでCTOが責任者としてまとめていた。
人間関係には恵まれていたが、スケジュールがややキツかった。
僕の勤務形態は週5フルタイム。フルリモート。休みが取りにくく、社会人になって初めて夏季休暇が取得できなかった。
③スタートアップC
既にサービスはローンチされていたが、まだ一般公開されていなかった。取引のある顧客にだけ開放していた。実質、大手企業からの受託案件が売上のメインとなっている会社でした。
僕が参加した時点で創業5年。社員は3名で、内1名がエンジニア。この人の退職に伴い、僕が後任となった。
新しい技術をどんどん取り入れる会社で、スキルは向上する環境であった。しかし、人数が少ないこともあり苦手な仕事でもハイレベルな結果を求められ、厳しい言葉をかけられることも多かった。個人的には、お世辞にも働きやすい環境ではなかった。
勤務形態は週5フルタイム。月、火曜日のみオフィス出社。
②のスタートアップBよりもさらに休みは取りにくく、夏季休暇を取得しようとして少し揉めた。
スタートアップの特徴
会社によって特色はあるものの、これまでお世話になったスタートアップで共通している特徴は以下の通りです。
仕様変更が多く、その意思決定も早い
サービスからの売上がない、又は売上が安定していない企業ほどこの傾向が強い印象です。
大幅な方針転換をするケースも珍しくなく、ローンチしたサービスが当初想定したものとはまるで違うものになっていたこともありました。
また、大企業と違い、小回りが効くので意思決定のスピードも早いです。創業者の意向が強く反映されるため、創業者が「こうしたい」と言えば、すぐにその方向に方針転換するケースが多かったです。
ただ、度重なる方針転換によってメンバーがついて行けず、軋轢を生む要因になっていたケースもありました。それによってエンジニアが大量離脱するということもありました。
スピード重視
スタートアップの経営者はこれから参入しようとしている領域、参入した領域に大手企業が入ってくることをとても警戒しています。資金面や人的リソースなどあらゆる面で大手企業と勝負しても勝ち目がないからです。
そのため大手が入ってくる前に顧客を獲得したいため、スピードを重視する傾向があります。ある程度の品質は目を瞑って、とにかく早くサービスをローンチすることを重視します。
役割の範囲が広い
大手の案件だとフロントエンド、バックエンド、インフラなど役割がしっかりと分けられていることが多いですが、スタートアップの場合は兼任することが多いです。特に会社規模が小さいほど人数が少ないので1人の役割が多くなります。特定の分野だけでなく、様々な分野の知識を身につけられるチャンスでもあります。
ただ、完全属人化して、ワンオペとなるケースもあります。そうなると身動きが取りづらくなるので要注意です。
モダンな技術を使うことが多い
サーバーはAWSやGCPなどのクラウドを使用することがほとんどです。
プログラミング言語もPython、Go、Rubyを使用しているケースが多く、フロントエンドはReactやVueと言ったフレームワークを使用していました。同時にTypeScriptも導入していました。ソースコードの管理はgithubを使っています。
またAI関連やブロックチェーンなどを活用していることも多く、比較的新しい技術に触れられる可能性は高いと言えます。
SNSでの発信内容はやや誇張気味
SNSでスタートアップの経営者をフォローしていると「○○万円資金調達しました!」「○○に採択されました!」「○○(超有名企業)出身のA氏が参画しました!」のような投稿を目にすることがあります。
このような投稿を見ると「この会社、うまく行っているんだな」「稼げているんだな」と思ってしまいますよね。しかし、実態は全くサービスからの売上の見込みが立っていなかったり、人の入れ替わりが激しかったりして、イメージとは異なることも珍しくないです。
決して嘘の発信をしているわけではないです。書かれていることは本当のことです。ただ、少し表現を誇張し過ぎなんじゃと思うことも多いです。会社の認知度を上げるための大切な広報活動でもあるのですが、「ちょっと大げさにアピールしている部分もある」ということを認識しておくことをおすすめします。
休みが取りにくい
スピード重視のため、スケジュールはややキツめです。
僕がお世話になった会社は、残業はほとんどなく、休日出勤もなかったのですが、スケジュールに余裕がなかったため、平日に休みを取得したり、夏季休暇のような長期休暇は取得できませんでした。
自分だけでなく、周りもほとんど休暇を取得していなかったので、休みが取りにくい印象は強いです。
リモートワークが多い
スタートアップの場合は何人も入れるオフィスを持っているケースは少ないので、基本的にリモートワークでの仕事が中心になります。
PCは自分のものを使用する
大手の案件に参画すると、大抵は開発用のPCが支給されますが、スタートアップの場合は自分のPCで開発することになります。支給してくれる会社もあるかもしれませんが、少なくとも僕がお世話になった会社は自分のPCを使っていました。
そのため、開発をスムーズを行えるスペックのPCを所有している必要があります。OSはWindowsでもMacでも大丈夫です。
コミュニケーションツールはSlack
コミュニケーションをとるためのツールはSlackです。
日報などの提出を求める企業においても、今は全てSlackになっています。仕様の確認や会議開催の周知などの連絡事項もSlackで行われます。以前はメールで行われていたものが、全てSlackになってますね。
スタートアップでの仕事に向いている人
最新の技術に触れていたい人
スタートアップではモダンな最新技術を採用していることが多いので、新しい技術触れて知識を身に着けて行きたい人には良い環境です。AIなど今話題の知識を身につけるチャンスに恵まれる可能性も高くなります。
とにかく仕事が好きな人
スタートアップで働いている人は「仕事が趣味」というくらい仕事への情熱を持っている人が多いです。仕事が好きな人にとっては働きやすい環境だと思います。
幅広い分野の知識を身につけたい人
特定の分野(例:バックエンド、インフラなど)に特化するのではなく、フルスタックで幅広い分野の知識を身につけたい人にとってもスタートアップは良い環境だと言えます。
大手の案件だと役割が固定されていることが多いので、やりたいことがやれないという不満が溜まる可能性があります。
また、特にSESの場合は即戦力を求めている関係上、これまで経験したスキルの切り売りになることが多く、実務で扱ったことがない技術を使用する案件に参画するのは難しくなります。
スタートアップの場合は、1人の役割の範囲が広い分、ある特定の技術を持っていれば、他の技術は勉強しながらやってもらえれば良いというケースもあり、実務で扱ったことがない技術の実務経験を積むことができる可能性が大手の案件よりは高いです。
覚えることが多くなり大変な部分もありますが、そこが苦にならないのであればチャンスです。
スタートアップに向いていない人
仕事とプライベートは完全に分けたい人
上記で記述した通り、スタートアップには「仕事が趣味」というくらい仕事への情熱が強い人が多いです。なので、休日とか関係なく仕事をしている人も珍しくなく、休日でもSlackに連絡が来ることもあります。
また、特に長期休暇が取得しにくいという特徴もあります。
そのため、仕事とプライベートは完全に分けて、たまには休みを取って旅行に行きたい、リフレッシュしたいという人には、それが難しくなりストレスが溜まる要因になります。
チーム体制、ルールが明確に決められた環境で働きたい人
スタートアップの場合は人数が少ないため、一人の役割が多くなる傾向があります。また、最低限のルールしか定められておらず、曖昧になっていることも少なくないです。
そのため、決められたルールの中で自分の力を発揮して行きたい人。チーム体制がしっかりと構築されていて、自分の役割が明確になっている中で仕事をしたい人には向かない環境です。
安定を求める人
大手企業に比べるとスタートアップの経営状況は脆弱です。思うように売上が立たず、契約終了となることもあります。給与や単価を下げられてしまうこともあります。
たとえサービスの売上が安定していても、そのサービスがいつ廃れてしまうかも分かりません。スタートアップで収益の柱が複数ある会社は少ないです。
そのため、安定した環境で長く仕事をしたい人には不向きな環境です。
まとめ
あくまで僕がお世話になった3社での経験を元に書かせて頂きました。
スタートアップと言っても、それぞれの会社で規模も違うし、文化も異なります。なので、上記の「向いている人」「向いていない人」が当てはまらない会社もあると思います。「このような可能性が高い」というご認識をして頂き、参考にして頂ければ幸いです。
尚、基本的にスタートアップの経営者は皆さん優秀な方が多いです。リスクを覚悟で行動していている方々なので、個人的には本当に尊敬しています。自分には絶対にできないことなので。
そう言う意味で、そのような方々と一緒に仕事をして、話を聞いて、その考え方を聞いたりすることで刺激を受けたり、勉強になることも多いです。

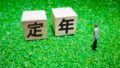

コメント